食べ物によって違うβグルカンの機能
現代の日本は大変豊かになってきました。
世界の中でも豊かな国と言っても過言ではありません。
道路や水道や電気などのインフラストラクチャーも完備してきました。
その中で私達は快適な生活を送っている訳ですが、食べ物についても現在の日本では様々なものが食べられるようになりました。
またカロリーの摂取量も昔と比べると大変高くなってきています。
このように色んな面で恵まれた社会になっている現代の日本ですが、このような状況になってきたからこそ生じるような問題も発生しました。
その一つが、生活習慣病と呼ばれるものです。
生活習慣病というのは、運動不足の状態においてハイカロリーで高脂質で高糖質の食べ物を取ることで生じます。
多くの場合には、肥満や高脂質症や高血糖症などの病気になります。
これらの病気はそれだけでは差し迫った影響はないのですが、他の色々な病気を誘導する働きを持ちます。
高血糖症の場合には血管内に血栓が生じやすくなり、肥満や高脂質症の場合には癌などが誘起される事が知られています。
このような生活習慣病を改善するものとしてβグルカンが注目を集めてます。
βグルカンは大麦などの穀類やキノコ類や酵母や海藻類などに含まれますが、含まれる食べ物によって構造が少しだけ違っていおり、そのことから機能が違う事が知られています。
きのこ類に含まれるものでは、免疫向上や抗癌作用があるということが発表されました。
また大麦などに含まれるものでは、食物繊維として血糖値やコレステロールの低減などに役に立つと言われています。






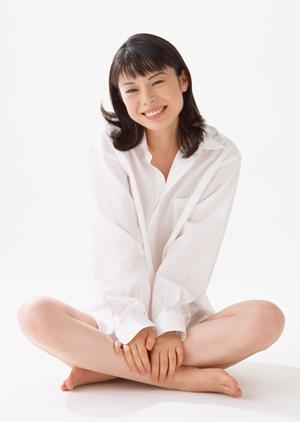


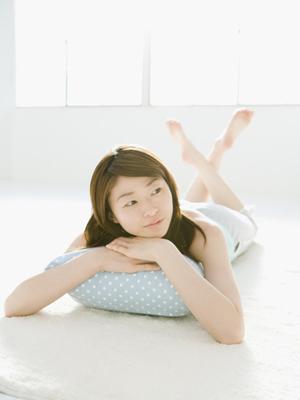























.jpg)





